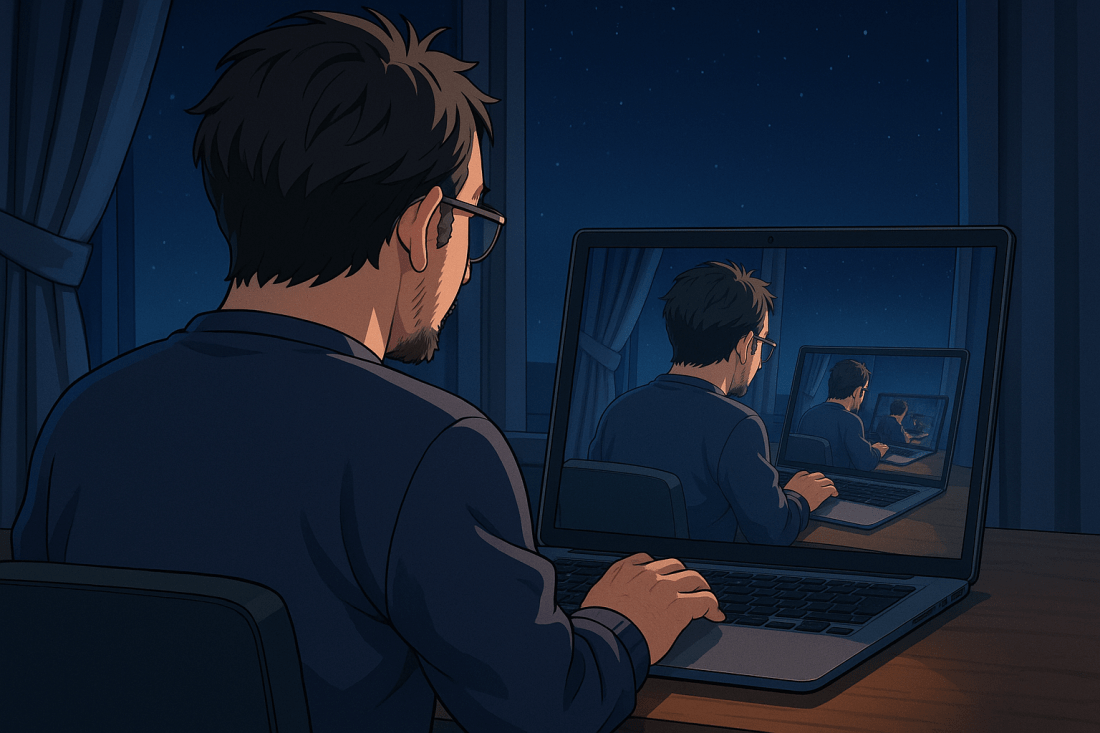プロローグ ── 見えない力
もし──この世界に「隠しコマンド」があるとしたら?
たとえば、神社でふと口にした願いが、実は何かに届いていたとしたら?
それが単なる迷信ではなく、目に見えない“仕組み”の一部だったとしたら?
そんなことを真顔で考えてしまう瞬間が、人生にはある。
たとえば、努力ではどうにもならなかったはずの現実が、なぜかすんなり動いたとき。
たとえば、理不尽の中に、ひと筋の光が差し込んだとき。
「たまたまだよ」「偶然さ」と笑ってやり過ごすこともできた。
けれど、その“偶然”が、あまりにも繰り返されると──
まるで誰かが僕の内心を読んで、微調整しているかのように感じ始める。
あの頃の僕は、そんな違和感すら抱けないほど、心が擦り切れていた。
でも今ならはっきりわかる。
あれは、始まりだった。
何が変わったのか? 僕自身か、世界そのものか。
それとも──僕の知らない「何か」が、そっと手を差し伸べていたのかもしれない。
第1章 ──2020年:最初の違和感

2020年。
世界は静かに狂い始めていた。
新型コロナの感染拡大により、街は音を失った。
人と会うことは罪のようになり、僕はひとり、家に閉じ込められた。
50歳の春。
体重125キロ。血圧は高め。不整脈あり。髪は薄くなり、白髪は隠しきれない。
平凡なサラリーマン。一人暮らし。恋人なし。友達とも疎遠になり、酒量とネットの使用時間だけが増えていた。
「まぁ、人生なんて、こんなもんだろ」
そう呟いてみても、何かが胸の奥で引っかかっていた。
それは諦めではなく、鈍い痛みのような「未練」に近かったのかもしれない。
それでも日々は過ぎていく。
唯一の外出は、夕方の犬の散歩だった。
その日も、いつものようにリードを握り、家を出た。
けれど、なぜか犬がいつもと違う方向へ歩き出した。
引っ張られるままについて行くと、見知らぬ小道に出た。
そして、突然──神社が現れた。
鬱蒼とした木々に囲まれ、ひっそりと佇むその境内。
こんなところに神社があるなんて、今まで気づかなかった。
不思議と、足が止まった。
古びた石段の先にある鳥居だけが、妙に新しく、異質に見えた。
気のせいかもしれない。けれど、その“違和感”が、僕の心をほんの少しだけ揺らした。
それから、散歩コースは変わった。
気づけば、毎日のようにこの神社に立ち寄り、お参りをするようになっていた。
無人の境内。風に揺れる鈴の音。
誰にも聞かれないとわかって、僕はふっと笑いながら、願った。
「このままじゃ、終わりたくない」
「痩せたい」
「見た目を変えたい」
「──誰かに、好かれたい」
小声で、でも、確かに本音だった。
すると、風が強く吹いた。
木々がざわめき、鈴が一際高く鳴った。
「…偶然だよな」
そう思いながらも、背中に残る感触だけが、妙に離れなかった。
──それから少しずつ、何かが変わり始めた。
ごくわずかな、でも確かな“ちがい”。
あの時はまだ、それが「プログラムの応答」だとは、思ってもいなかった。
第2章 ── 2021年:変化という『仕様』
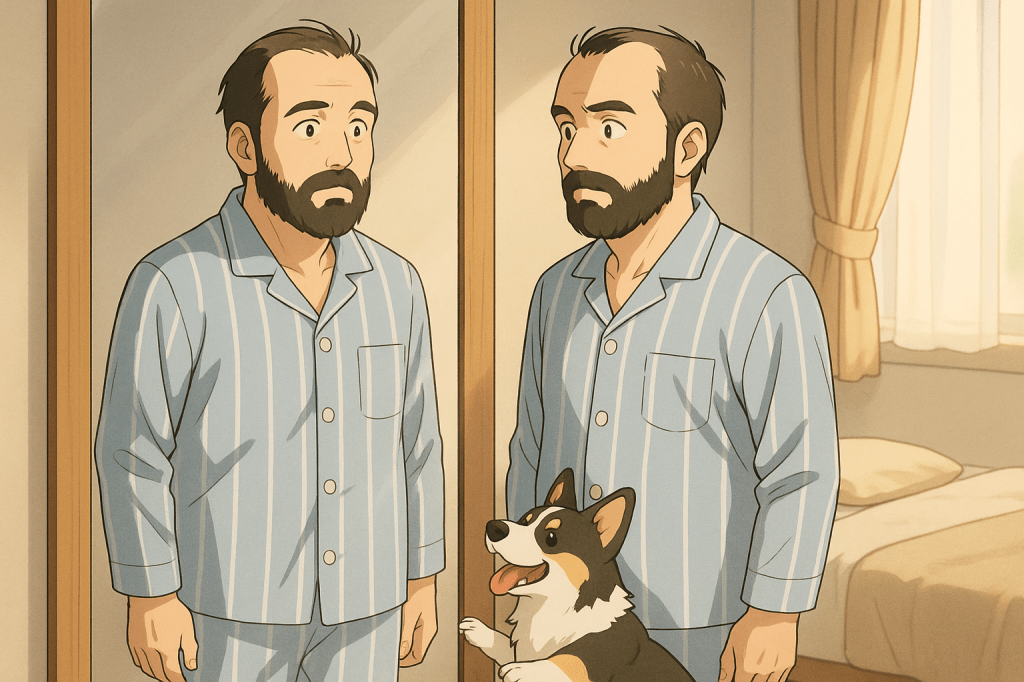
運動なんて、これまで何度挫折したか覚えていない。
けれど、神社で願ったあの日の翌朝、ほんの少し違っていた。
不思議と、「動きたい」という欲求が湧いてくる。 昨日までの僕なら、二度寝を選んでいたはずなのに。
特別な決意があったわけじゃない。ただ、ふとYouTubeで見かけた宅トレ動画を再生してみた。
気づけば毎朝、腹筋とスクワットを繰り返えすようになった。
筋肉痛が、嬉しかった。
鏡の中の僕に、少しずつ変化が現れはじめた。
輪郭がほんのり締まり、Tシャツの裾が浮かなくなってきた。
「痩せた?」「なんか若返った?」
そんなふうに言われるたび、心のどこかがくすぐったかった。
──ただの偶然だ。
努力の成果。サボってた僕が、ようやく真面目になっただけ。
そう言い聞かせていた。でも、否応なく浮かんでくるのだ。
あの神社の、小さな鈴の音。
あの日、風が吹いたときの空気の揺れ。
「まさかね」
そう呟いた舌の奥に、言い切れない予感が残った。
そしてもうひとつ、不可解な変化が始まっていた。
薄くなった額の生え際──そこに、柔らかい産毛が戻ってきた。
AGA治療薬は、まだ手を出していない。
食生活も変えていないし、サプリも飲んでいない。
「……これは、偶然?」
あの日と同じ神社へ、僕は再び足を運んだ。
鳥居をくぐった瞬間、空気がほんの少し、張りつめたように感じた。
前回よりも、願いはずっと具体的だった。
「髪が、ちゃんと生えてきますように」
声に出すのが恥ずかしくて、心の中で強く唱えた。
──今度は、風は吹かなかった。
鈴も鳴らず、ただ静かな夕暮れの空気がそこにあった。
けれど、不思議とがっかりはしなかった。
むしろ、何かがすでに作動しはじめている──そんな確信が、胸の奥にじわりと広がっていた。
偶然かもしれない。でも、もしそうじゃなかったら?
世界のどこかに、“仕掛け”があるのだとしたら──。
僕の人生は、ほんの少しだけど、「仕様」が変わり始めていた。
第3章 ── 2022年:欲望のテンバガー
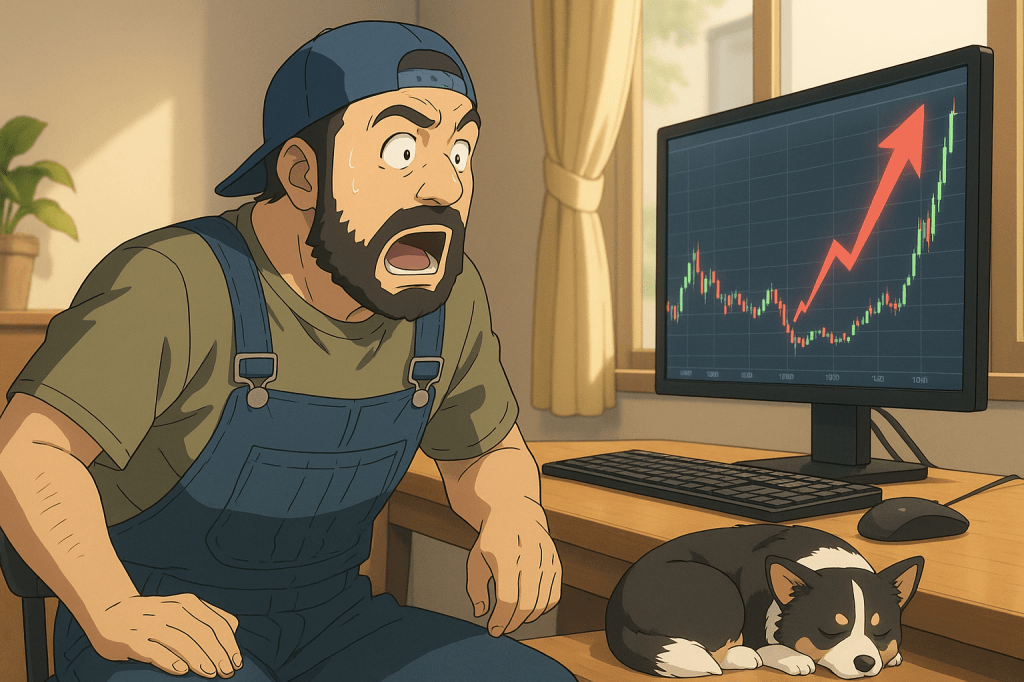
髪は、明らかに増えていた。
前髪の密度が変わっただけでなく、生え際にうっすらと産毛が並んでいるのが分かる。
美容室の椅子に座ったとき、担当のスタイリストが首をかしげた。
「何かしてます? 薬とか…植毛とか?」
「いや、体質改善ですかね」と、僕は笑ってごまかした。
けれど、内心では鼓動が高鳴っていた。
──効いてる。あの願い、ちゃんと届いてる。
嬉しさと同時に、妙なざわめきが胸の奥に残っていた。
これは自分の努力の結果なのか? それとも──神社?
否定しようとする理性の声を振り払うように、次の願いを考えた。
髪と見た目を手に入れた。なら、次は──
お金だ。
神社の鳥居をくぐるとき、かすかに風が吹いたような気がした。
今度は五百円玉を握りしめ、少しだけ真剣な表情で手を合わせる。
「テンバガーが欲しいです。お願いします」
テンバガー──株価が10倍になる銘柄。
夢のような言葉だ。だけど、僕には確信があった。
「願えば動く」──そんな世界に、今いる。
もちろん、投資の素人だという自覚はあった。
それでも、いくつかの銘柄を調べ、業績やテーマを読み、わずかな資金で数社に分散投資した。
どこかで、「願っただけじゃダメだ」と思う自分もいた。
自分で考えた。自分で判断した。だから、結果が出ても偶然じゃない──と、思いたかった。
それでも、その年の秋、小型株のひとつが異常な上がり方をした。
掲示板でもほとんど話題になっていなかったその銘柄が、突如として急騰したのだ。
──買った翌週から、株価は止まらずに上がり続けた。
「……まさか」
心のどこかで、その言葉が浮かびそうになるのを、ぐっと飲み込んだ。
冷静にチャートを見つめ、ニュースの影響を分析しようとする自分。
一方で、あの神社の石段を、なぜか思い出してしまう自分。
利益は、年収を超えた。
「本当に、祈ったから?」
半信半疑。けれど、手は震えていた。
合理的な説明ができないことを、心の奥が知っていた。
再び神社を訪れたのは、年末の夕暮れだった。
寒さの中、石畳を歩きながら、僕はふと立ち止まった。
鳥居の朱色が、夕日に照らされて深く沈んで見えた。
この場所には、何かある。
この神社だけが持つ、何か「仕様」のようなものが──
五百円玉を賽銭箱に落とす音が、木霊する。
僕は静かに手を合わせた。
「本当に、ありがとう」
その瞬間、自分がどこにいるのか、わからなくなった。
現実の中の夢か、夢の中の現実か。
でも──確かに、何かが動いていた。
僕の人生が、静かに、しかし確実に軌道を変え始めていた。
第4章 ── 2023年:告白と確信
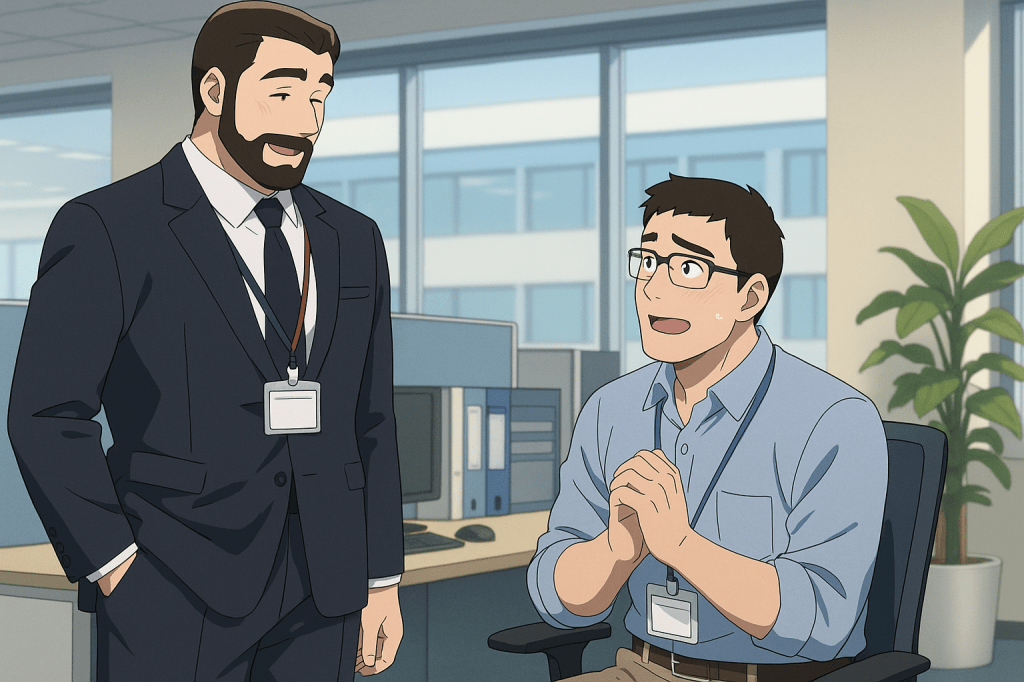
お金が入ると、景色が変わる。
服を選ぶときに値札を見なくなった。
気になる展示があれば、その日のうちにチケットを取った。
髪型や体型にも気を遣い、鏡の中の自分がほんの少しだけ好きになっていった。
そして、もうひとつ変わったものがある。
人の目だ。
ある日、職場の後輩──僕が密かに思い続けてきた彼が、不意にこう言った。
「はやとさん、最近ほんとカッコよくなりましたよね。……モテるでしょっ!」
一瞬、時が止まった。
冗談? いや、本気の目だった。
何かが胸の奥で弾けた。
そういえば──あの神社で、願った。
「彼と、付き合いたい」
願ったのは、それだけだった。
その日の帰り、神社に寄った。
夕暮れの鳥居の前に立ち、そっと手を合わせる。
「どうか……」
風が吹いた。
枝を揺らす音が、耳にやさしく触れる。
その音を、僕はどこかで覚えていた。
週末、彼から食事に誘われた。
ごく自然な流れで、互いの気持ちを確かめ合う時間になった。
気づけば、付き合うことになっていた。
……できすぎている。
まるで、何かの筋書きに沿って動いているようだった。
僕は思った。いや、もう確信していた。
この神社は、願いを叶える。
ただの偶然なんかじゃない。
それを信じずにはいられないほど、あまりに綺麗に、物事が動いていた。
そして、この確信が、僕の世界をさらに広げていくことになる。
第5章 ── 2024年:報復の副作用

願いが次々と叶っていく中で、僕の人生はまるで物語の中にいるようだった。
体型も変わり、髪も戻り、株で資産も手に入れた。
まさか──こんな人生が自分に訪れるとは。
けれど、ひとつだけ引っかかる“影”があった。
それは、友人Aの存在だった。
学生時代からの付き合いで、昔から僕を小馬鹿にする癖があった。
痩せたときも「どうせリバウンドするだろ」、
筋肉がついたら「加工だろ」、
髪が増えたときも「カツラだよな?」とニヤついた。
他人から見れば些細な冗談かもしれない。
でも、僕にとっては過去の自分を揶揄されているようで、どうしても心に刺さった。
──そしてある夜、ふとした気のゆるみで、神社の境内でこう願ってしまった。
「……アイツに、ちょっとだけ痛い目を見てほしい」
自分でも驚くほど自然に口から出た言葉だった。
それは、深い恨みでも憎しみでもなく、ただ小さな“仕返し”だった。
あの日は風も吹かなかったし、鈴も鳴らなかった。
でも、数週間後──共通の知人からこう聞かされた。
「Aさん、詐欺に遭ったらしいよ。かなりの額をやられたって」
息をのんだ。
「……まさか……」と思いかけて、すぐに打ち消した。
だが、心のどこかではうっすら確信してしまっていた。
願いが、また叶った──と。
胸の奥がざわざわと揺れた。
嬉しいという感情ではなかった。むしろ、不安に近い。
悪意をもって願ったことも、叶ってしまうのか?
その事実は、神社の“力”の精度をさらに強く証明してしまった。
この日から、僕の中で小さな歯車がきしみ始めた。
願いが叶う喜びは確かにあった。
でも、そこに少しずつ「制御不能な力」への畏れが混じり始めていた。
それでも──。
神社に通うことはやめなかった。
怖さよりも、次に願うことの期待のほうが、少しだけ勝っていた。
それはまるで、自分の人生を裏から設計し直しているような感覚だった。
どこまでが自分の意志で、どこからが「設計された現実」なのか──
それすらも、だんだん曖昧になっていった。
第6章 ── 2025年:復讐という『因果』
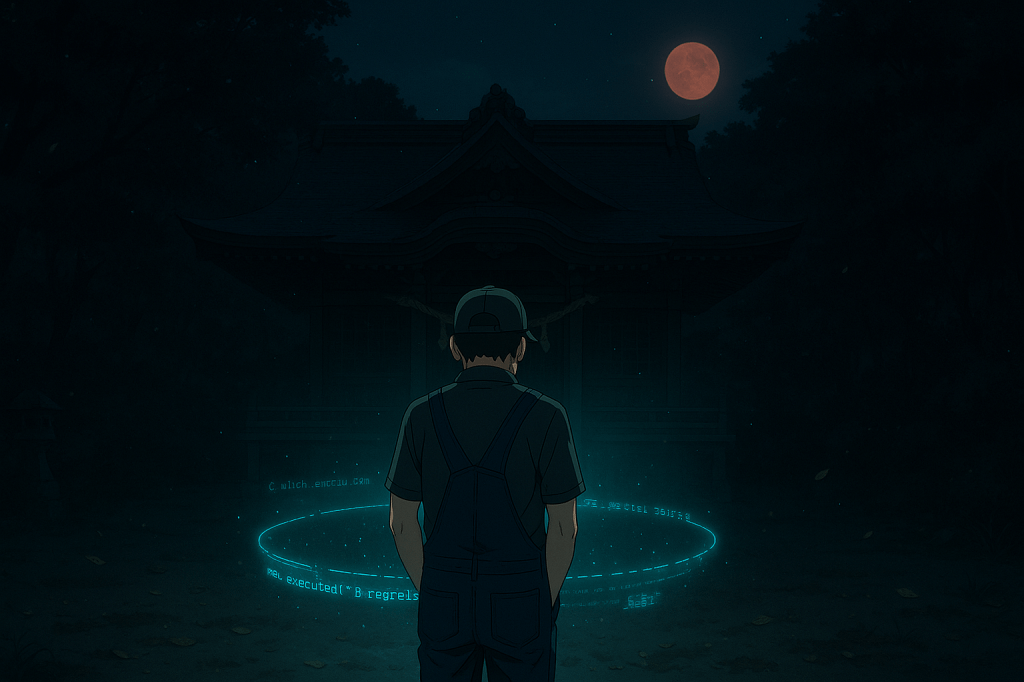
願いは、たしかに叶った。
けれど、心の中には、冷たいものが残っていた。
あの夜、僕は神社でひとことだけ願った。
「Bが、後悔しますように」と。
──それだけだった。
それからしばらくして、Bから連絡があった。
学生時代、僕の恋心を茶化し、笑いものにした相手。
「ゲイだって、みんなに言ってやろうか?」と脅すように囁いた彼からの突然のメッセージ。
「……ごめん。あのときのこと、本当に悪かったと思ってる」
謝罪の言葉だった。
でも、その声は反省というより、怯えの混じったものだった。
何があったのかは、あえて聞かなかった。
どんな出来事が彼に謝罪を促したのか。
──でも僕は、もう知っていた。
あの神社で願ったことが、またひとつ、現実になったのだ。
それでも、僕はスッキリしなかった。
むしろ、妙な虚しさが広がっていた。
「これが、僕の願いの結果なのか……?」
ふと、そんな言葉が浮かぶ。
復讐とは、痛みの交換だ。
誰かを傷つけた代わりに、自分の中の苦しみが少し軽くなる──
そんな幻想を信じていたのかもしれない。
でも現実は、そうではなかった。
“叶う”ということは、“起きる”ということだ。
しかも、それが自分の意志に由来しているとすれば──
それは、責任を伴う現実改変だ。
いつしか僕は、自分の人生が「操作可能」なもののように感じ始めていた。
たとえば、朝の通勤電車で優先的に座席が空く。
たとえば、行列の先で最後のひとつの商品が残っている。
たとえば、思っていた人から、思っていたタイミングで連絡が来る。
些細な偶然が、あまりにも“思い通り”すぎた。
願った記憶すら曖昧な時でさえ、結果が先に応じてくる。
それは、まるで──シナリオに沿った演出のようだった。
この“現実”は、いったい誰の手の中にあるのだろう?
もしかして、これはただの人生ではなく、何者かが設計した“体験プログラム”なのではないか。
そして僕は、意図せずその設定値を書き換えてしまっているのではないか。
いや、もっと正確に言えば──
僕自身がこの世界の仕様を上書きしているのではないか?
気づけば、僕の心の奥には静かにこうした問いが根づいていた。
願えば叶う。
叶えば、誰かが動く。
動けば、現実が変わる。
そして、変わった先には、また別の因果が生まれる。
僕の望みのひとつひとつが、まるでコードの一行のように、世界を少しずつ改変している。
──ならば、僕は一体、どこまでを願っていいのだろう?
そして、この世界は、いったい──どこまで“書き換え”に耐えられるのだろう?
第7章 ── 2026年:社会という「拡張」
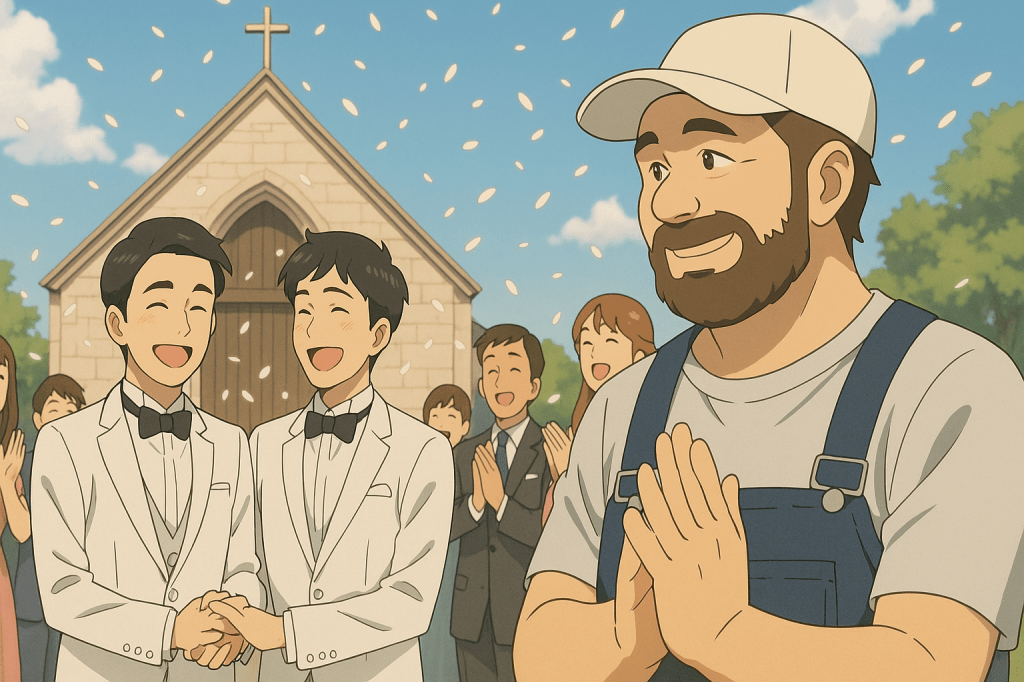
「同性婚、そろそろ認められてもいいんじゃない?」
彼がそう言ったのは、年始にふたりで訪れた伊勢神宮でのことだった。
大きな鳥居をくぐりながら、僕たちは手をつないでいた。周囲の目が気にならなかったわけじゃない。でも、それよりも「こうして一緒に来られること」が、ただ嬉しかった。
駅でも、旅館でも、僕たちは“ただの男同士”として扱われていた。
けれど、彼の隣にいる僕は、誰よりも自然に笑えていた。
──それでも、心のどこかに、小さな棘のような引っかかりがあった。
法律で認められていないこと。
病院で「家族ではない」と言われるリスク。
財産のこと、老後のこと、そして──万が一別れたときのこと。
「神社に、願ってみようかな」
そう言った僕に、彼はちょっと笑った。
だけど僕は、本気だった。
その夜、横浜に戻ってから、僕はいつもの小さな神社へ向かった。
「同性婚が、認められますように」
そう願った。
僕の祈りは、もう自分の見た目やお金のことではなかった。
別の日には、こうも願った。
「日本経済が回復しますように」
「孤独な人が、希望を持てますように」
願いのスケールが、自分自身の外へと広がっていく。
まるで、かつての僕が持ち得なかった「世界に対する影響力」を、今になって手にしたような──そんな錯覚。
そして、それが錯覚ではないような出来事が、次々と現実になっていった。
ニュースのヘッドラインに躍る「同性婚、議論再燃」の文字。
国会での討論。
保守派からも「慎重な検討を」の声が聞こえ始めた。
円安が落ち着き、海外企業が再び日本に拠点を構え始める。
若者の就職率が上がり、自殺率が過去最低を記録したという報道。
たまたまなのか?
それとも、あの祈りが“反映”されたのか?
──わからない。でも、ただの偶然とは思えなかった。
神社は変わらず静かだった。
でも、空気が以前より澄んでいる気がした。
まるで、祈りを吸い込んだ木々が、少しずつその答えを吐き出しているような。
気づけば、僕は「叶える力」の使い方を、慎重に選ぶようになっていた。
誰かを傷つけるような願いは、もう二度としない。
誰かの幸福を、社会の幸福を願うことで、自分の存在を許せる気がした。
この“力”があるなら──
僕たちの未来も、社会の希望も、変えられるはずだ。
そう信じていた。
第8章──2030年:「叶った世界」と、残された者

2030年。
僕は60歳になっていた。
毛も、金も、健康も、彼も──
何も持っていなかった。
同性婚は実現していないし、日本経済は漂流していた。
かつて夢見た「自由で豊かな老後」とは真逆の、乾いた現実。
空の冷蔵庫と、誰も鳴らさないスマホだけが、日々の背景になっていた。
だけど、もう一人の“僕”は違った。
モニターの中。
箱庭で生きる2020年からの「僕」は、
願いのすべてを叶えていた。
──そう、それは現実の僕が設計した「もしも」の仮想世界。
その中の「僕」が神社で祈った願いが、すべて叶うように組み込んでおいた、ひとつの箱庭シナリオ。
その箱庭の中の「僕」は、理想の彼と暮らし、
自宅は快適で洗練された空間に整えられ、
社会的にも尊敬され、健康は若返ったように保たれ、たくさんの友人に囲まれていた。
言葉ひとつで人を動かし、未来を変えていた。
誰もが豊かな生活を送っていた。
「うらやましいねぇ……」
僕は冷めた目で呟いた。
画面の中の「僕」は笑っていた。
その笑顔は、僕のものではなかった。
僕は観察者であり、設計者だった。
自分の過去を素材に作った仮想シナリオ。
数百行の条件分岐とリクエストで構成された、
「叶うこと」が保証された世界。
指先の操作で、箱庭の時を進める。
2030年。ちょうど今日と同じ日。
理想の人生を生き続けてきた「僕」は、
まだ完璧な笑顔のままなのか──
その確認のつもりだった。
けれど、そこには異変があった。
箱庭の中の「僕」は、いつものように朝のコーヒーを淹れていた。
ガラス張りの窓から海が見える。犬が足元で眠っている。
完璧な日常。
……のはずだった。
だが、その「僕」は、どこか違っていた。
ふと顔を上げて、空を見た。
その表情に、ざらりとした違和感が走る。
笑っていない。むしろ──戸惑っている。
彼はパソコンを開き、なにかを調べている。
量子処理、自己認識アルゴリズム、仮想環境の設計履歴……
そして、つぶやいた。
「ここ、なんか変だな……
もしかして、全部、作られている……?」
現実の僕の指が止まった。
画面の中の「僕」が、箱庭の「不自然さ」に気づき始めていた。
「……誰が、僕を走らせてる?」
その瞬間だった。
現実世界の僕の胸に、突き刺さるような寒気が走った。
あの「僕」は、仮想の存在。
それを作ったのは、今ここにいる“僕”……のはずだった。
でも、その“彼”が疑問を持った今、僕にも同じ問いが芽生える。
「じゃあ、この“現実”は……?」
モニターの電源を切る手が、少し震えていた。
僕は観察者だと思っていた。
自分が走らせていると思っていた。
でも、もしそれすら幻想だったとしたら?
僕が走らせていた仮想の「僕」が気づいたのと、
同じ時に、僕もまた“気づかされた”のかもしれない。
これもまた、誰かのシミュレーションではないか?
画面の光が消え、部屋が暗くなった。
でも、頭の中にはまだ、あの「僕」の声が残っていた。
「ここは、仮想かもしれない」
……いや、そうだとしても、
次に何を願うかは、まだ僕が決めていいのかもしれない。
仮想でも、本物でも。
願うことは、“僕”が“僕”である証なのだから。
📘 本気のFIRE・不動産投資・節税・退職ノウハウはこちら:👉 本編の目次を見る
☕️ 軽めの読みものをもっと楽しみたい方はこちら:👉 日常や気づきのエッセイ一覧へ